
カーボンシンクって初めて聞いた^^”

皆さん、こんにちは、ATARAプロデューサーの野村です。
突然ですが、カーボンシンクって聞いた事ありますか?
炭素吸収源と訳すようで、木だとか、海だとか、自然が吸収するCO2という生態系サービスのことです。
日本語で聞けばピンときますね^^”
今週、とある記事でを読んで、この言葉を知ったのですが、その記事のタイトルが衝撃的でした。
「バイオマス発電は再エネと認めない、EU規制強化へ」という記事。
EUの欧州委員会が、木材燃焼で発電する電力の一部を再生可能エネルギーから除外する方向の規制強化を検討していて、特に「no go area」と呼ばれる原生林の木を発電燃料として使うことは持続可能ではないため規制対象になるかもしれないというものです。
そして、EU指令の対象となる発電規模がこれまでの20メガワットから、小さな5メガワットまで規制対象を引き下げる方針でもあるようです。
実際にEUのバイオマス総発電量のうち、原生林由来の木材を使用する電力は約18%を占めるそうです。
記事からだとわからなかったのですが、エネルギーとして使うためだけに伐採されているのか、虫食いで資源として活用できない等の理由からエネルギー使用されているのか、その内容によってもずいぶん捉え方は変わりますよね。
18%というと、割とな率なので、これが対象から外れると、目標が~って議論にもなるのかもしれません。
ただ、再生可能エネルギーの比率を高めることが目的ではなく、CO2削減が目的なので、原生林の伐採がカーボンシンク(炭素吸収源)の機能を低下させる方がマイナスだという事で、環境活動家もそこを訴えているそうです。
それと、原生林の伐採は生物多様性も破壊しますしね。
さて、今後のEUの再生可能エネルギー指令含め、これらの改正はどうなることでしょうか!
また、結果が出たらニュースでも取り上げられるでしょうし、私も取り上げたいと思います^^
まだまだ勉強不足でもあるので、日本国内の現状も調べてみて、特に森林面積の41%が人工林という日本で、資源としての国産材の活用などについても考えてみたいと思います!
いずれ、考えてみたシリーズで勝手にお届けいたします^^




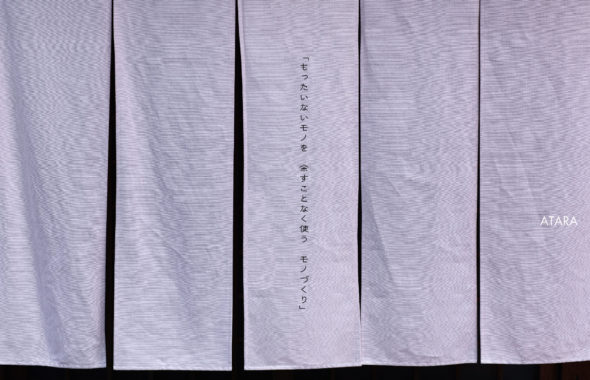



この記事へのコメントはありません。